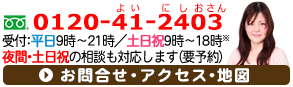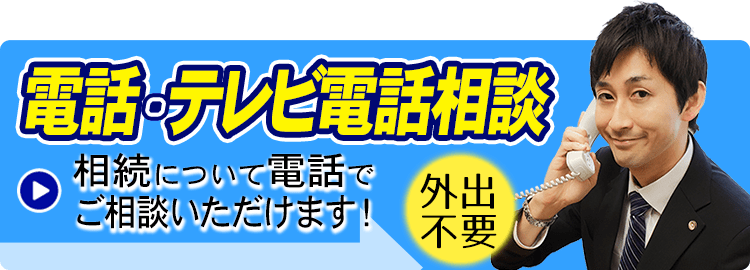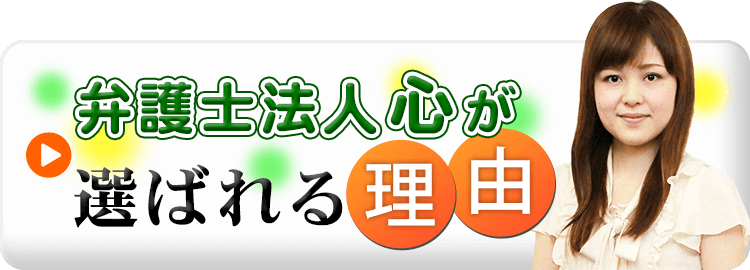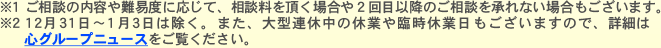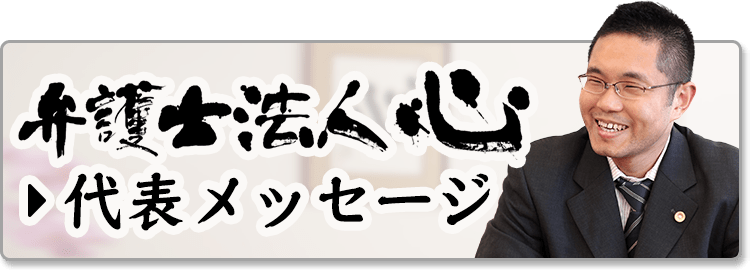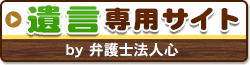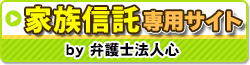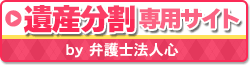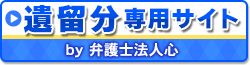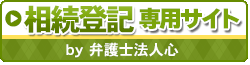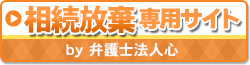相続手続きの種類と期限
1 身分関係の相続手続き
⑴ 死亡届の提出(7日以内)
死亡の事実を届出義務者が知ってから7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に手続きを行う必要があります。
届出義務者とは、亡くなった方(被相続人)の同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋又は土地の管理人です。
正当な理由なく届出期間内に手続きがされない場合、届出義務者には5万円以下の過料が処せられる場合があります。
⑵ 世帯主変更届(死亡から14日以内)
被相続人が世帯主(1つの住民票の中に記載されている世帯の代表者)である場合、新たな世帯主またはその世帯に属する人は、世帯主が亡くなってから14日以内に市町村長に新たな世帯主を届けなければならなりません。
正当な理由なく届出期間内に手続きがされない場合、届出を行うべき人に5万円以下の過料が処せられる場合があります。
2 財産関係の相続手続き
⑴ 相続放棄(3か月以内)
法律上、被相続人の財産を相続することが決まっている人(相続人)も、相続財産が借金の方が多い場合などの理由で相続したくない場合、相続をしない(相続放棄をする)ことが可能です。
ただし、相続放棄をするためには、被相続人の死亡の事実と自分が相続人であることを知った日から3箇月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に対し申述することで行います。
相続放棄をするつもりでも、この申述がされないまま上記の3箇月が経過すると、相続することを承認したものとして扱われてしまいますので注意が必要です。
⑵ 遺留分侵害額請求(1年以内)
一定の相続人には、「遺留分」として、被相続人の財産を受け取ることが保障されている取り分があります。
これにより、たとえ亡くなった被相続人本人が遺言などで、一部の人に財産を残したとしても、遺留分を有する人は、その財産を残された人に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
しかしながら、この請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効を援用された場合、時滅してしまいます(民法1048条)。
また、相続開始時から10年が経過した場合も同様です。
⑶ 不動産の相続登記(3年以内)*2024年4月より義務化
令和6年4月1日から施行される法律によって、令和6年4月1日又は、不動産所有権を取得したことを知った日いずれか遅い日から3年以内に不動産名義の登記変更をしなければならないことになります。
これを怠ると、10万円以下の過料を処せられる場合があります。
3 税金関係の相続手続き
⑴ 所得税の準確定申告(4か月以内)
確定申告を必要とする人が死亡した場合、その相続人は、その亡くなった年の1月1日から亡くなる日までに確定した所得金額と納税額を計算した上で、相続開始のあった日から4か月以内に被相続人の納税地を管轄する税務署長に対して申告と納税(準確定申告)をしなければなりません。
これを怠ると、延滞税(利息のようなもの)や加算税(適正な申告がされないペナルティのようなもの)といった税金を支払わなければならない場合がありますので注意が必要です。
⑵ 相続税の申告、納付(10か月以内)
相続財産の額によっては相続税を申告しなければなりません。
相続税の申告は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
これを怠った場合もまた、延滞税や加算税といった税金を支払わなければならない場合がありますので注意が必要です。
4 相続手続きのお悩みは弁護士へ
ここでご紹介したものは、ほんの一例です。
また、届出のものの中には添付すべき書類もあり、その取得にも日数がかかる場合もあるので、期限に余裕があるものでも速やかに手続きの準備を行わなければなりません。
加えて、明確に期限が定められていないものでも、手続きを行わないと、残された家族に大きな影響がおよぶものもあります。
例えば、会社員の父、専業主婦の母、未成年の子の3人家族でその父親が亡くなった場合、公共料金が父親名義の口座からの引き落としとなっていたとき、父親が亡くなりその口座が凍結され引き落としができない結果ライフラインが止まってしまう場合があります。
このような事態を防ぐために速やかに契約の名義変更等の手続きを行う必要があります。
身近な方が亡くなり少しでも相続手続きに不安のある方は、当法人にお気軽にお問い合わせください。