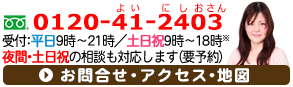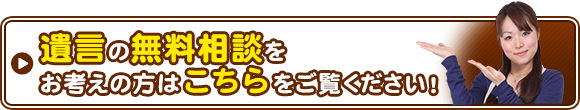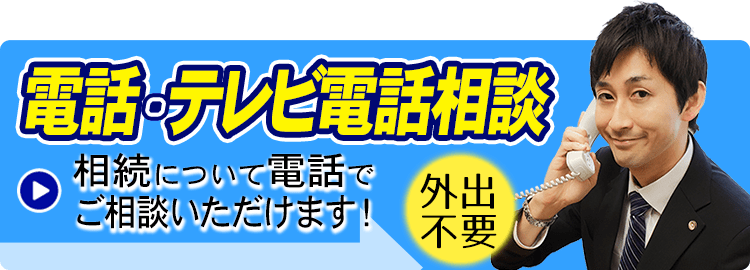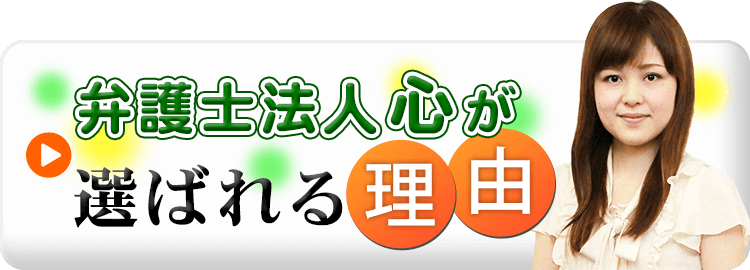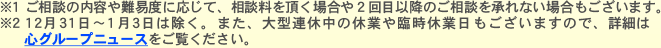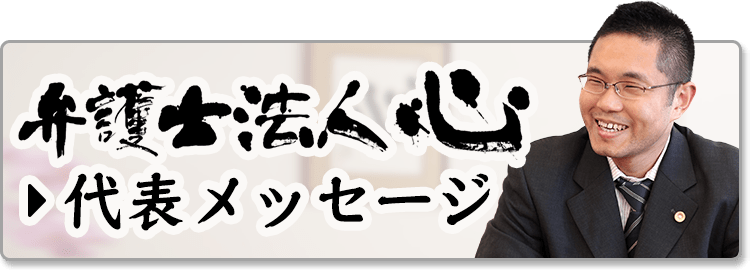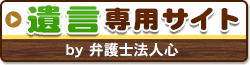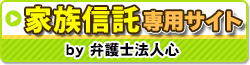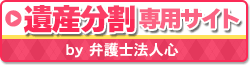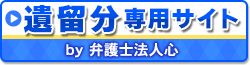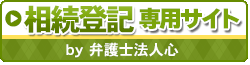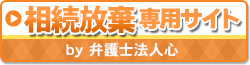弁護士に依頼して遺言を作成する流れ
1 全体的な流れ
これから遺言書を作成する場合に、どのような流れで遺言書を作成するのでしょうか。
この記事では、遺言書を作成する際には、公正証書遺言であることが多いため、公正証書遺言書の作成を弁護士に依頼するときの流れについて解説していきます。
まず、公正証書遺言を作成する流れは以下のとおりです。
- ① 依頼する弁護士の決定
- ② 遺言内容の決定
- ③ 文案の確認
- ④ 公証役場に行く日時の決定
- ⑤ 当日の持参物
- ⑥ 当日の流れ
以下、詳述していきます。
2 依頼する弁護士の決定
依頼する弁護士を決定する際注意するポイントとしては、相続分野を専門としている弁護士に依頼するという点が挙げられます。
通常、弁護士は「総合」法律事務所として、交通事故、離婚、相続、労働、建築等の多岐に渡る分野について対応していることが多いです。
しかし、中には、その内の一つの分野に絞って依頼を受けている弁護士も多いです。
例えば、「Aに〇〇の不動産を相続させる」と記載していた公正証書遺言について、Aが遺言者より先に亡くなり、後に遺言者が死亡した場合には、Aについての記載が無効になるため、Aの代襲相続人との関係で有効な遺言でなくなってしまった事案等もあります。
相続に強い弁護士であれば、代襲相続まで見越した遺言書を作成して対応することができたため、このようなミスをなくすことができます。
そのため、相続専門の弁護士を探して依頼することが合理的であるといえます。
3 遺言内容の決定
依頼する弁護士が決まったら、具体的な遺言書の内容を決定しましょう。
遺言の内容決定をする際の、重要なポイントは以下のとおりです。
- ① ご自身の財産を全て書き出す。
- ② 財産を渡したい人を全て書き出す。
- ③ (配偶者がいる場合)配偶者の生活費等について試算する。
- ④ (未成年の子がいる場合)未成年の子の生活費等について試算する。
相続人の方は、ご自身の財産がどのような状況になっているかを知らない場合もあります。
そのため、遺言書に記載する財産は漏れなく全部の財産を記載してもらうようにしましょう。
4 文案の確認
遺言の内容が決まったら、弁護士に対してその内容を送信し、遺言書の文案を作成してもらいましょう。
文案が出来上がったら、自身の考えている相続方法と一致しているか否かを必ず確認してください。
公正証書遺言の当日には、公証人が事前に遺言書の内容を印字した書類を作成しており、その場での修正が困難である場合もあります。
そのため、文案の確認自体を入念に行わなければなりません。
5 公証役場に行く日時の決定
文案の確認が終了した後、弁護士から依頼者様に対して、公証役場に行く日時の案内があります。
ご自身の都合の良い日時を指定して時間に余裕をもって作成するようにしましょう。
後述しますが、当日の持参物の失念等によって、スケジュールの再調整が必要になるケースもあるため、一日スケジュールを空けて置き、万が一の事態に対応できると良いです。
6 当日の持参物
公正証書遺言の当日の持参物は以下の通りです。
- ① 印鑑(印鑑証明書で本人確認をする際は、実印でなければなりません。)
- ② 印鑑証明書(本人確認書類を印鑑証明書とした場合)
- ②´マイナンバーカード又は、運転免許証、又は住民基本台帳カード(写真付き)(本人確認書類を印鑑証明書以外にした場合)
- ③ 公証役場の費用(5~7万円程度になることが多いです。)
- ④ 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- ⑤ (不動産がある場合)固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- ⑥ (不動産がある場合)登記事項証明書
- ⑦ (遺贈する場合)受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
- ⑧ 預貯金等の通帳のコピー
具体的な必要書類は、事案によって異なる場合がありますので、必ず弁護士に確認するようにしましょう。
参考:日本公証人連合会
遺言執行者を弁護士にする場合のメリット・デメリット 財産が不動産しかない場合の遺産分割の方法