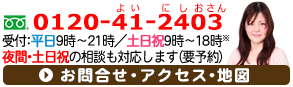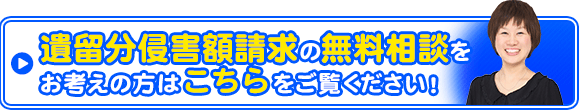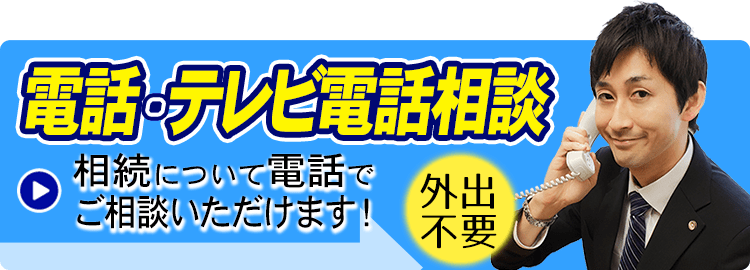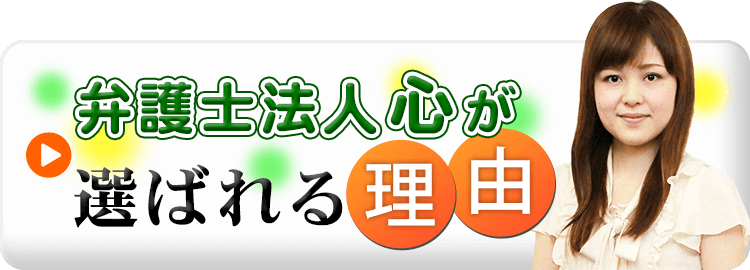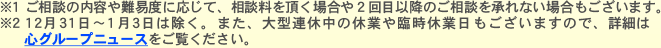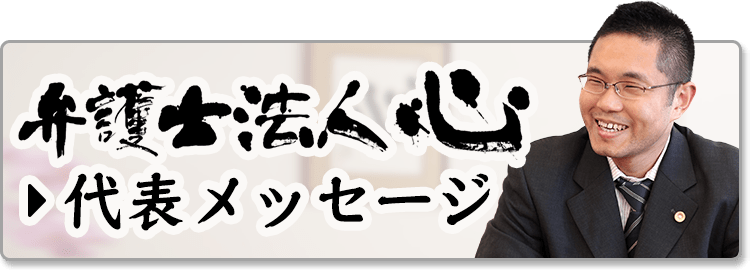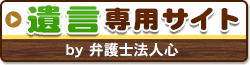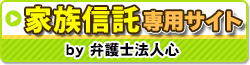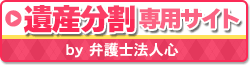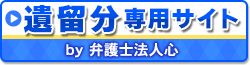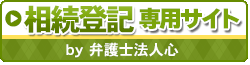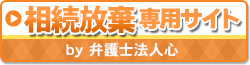遺留分の時効についてのQ&A
遺留分はいつまでも主張する事ができるのですか?
遺留分にも時効があるので、いつまでも主張できることはありません。
遺留分の時効には、以下の3種類の時効があります。
① 遺留分権利者が、相続の開始があったこと及び遺留分を侵害する事実を知った時から1年
② 相続の開始があった時から10年
③ 遺留分侵害額請求を行使できるようになってから5年
以上のように、遺留分には時効がありますので、遺留分の存在を知った際には、なるべく早く行使の意思を明確にして、遺留分を確保できるようにしましょう。
遺留分権利者が、相続の開始があったこと及び遺留分を侵害する事実を知った時から1年について、詳しく教えてください
遺留分権利者が、遺留分の存在を知っても、その権利を1年間放置していた場合には遺留分を行使する事ができなくなります。
ただし、この時効が起算されるためには、遺留分権利者が相続の開始を知っていただけでは足りず、遺留分を侵害する遺贈や死因贈与、遺言の存在を認識し、遺留分を侵害している事を認識している必要があります。
相続の開始があった時から10年について、詳しく教えてください
遺留分を侵害する贈与、死因贈与、遺言があった場合で、遺留分権利者がその存在に気づかないまま、相続開始後10年が経過してしまった場合には、その時点で遺留分を行使する事ができなくなります。
これは、民法上、除斥期間といい、その10年の間に遺留分に関わらない裁判の提起等を行っていても、時効の停止が起こらない期間となっています。
そのため、遺留分があるか明確に判断できないが、相続開始から10年が経過しそうな場合には、遺留分を請求する旨の裁判を提起する等の方法で、遺留分を行使する旨の意思表示を明確に行うことが重要です。
遺留分の放棄に関するQ&A 相続財産はどのように調査すればいいですか?