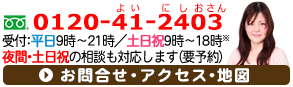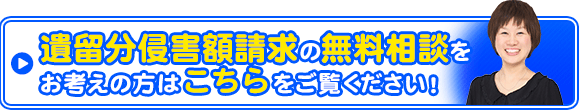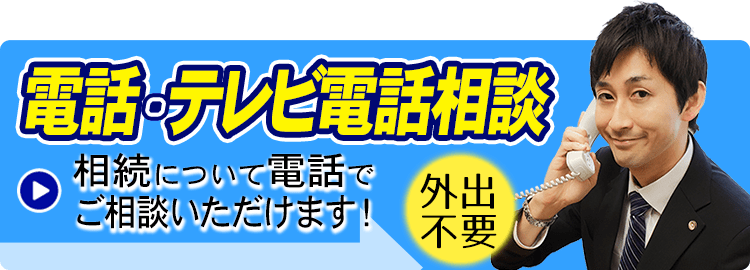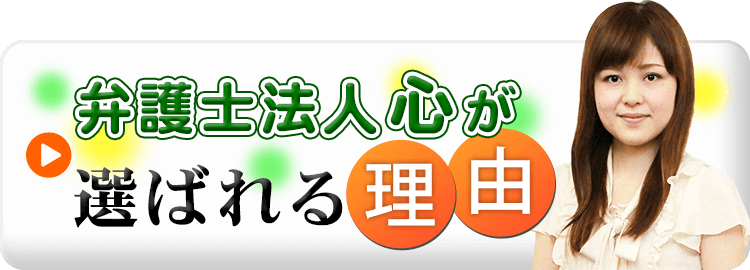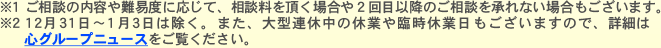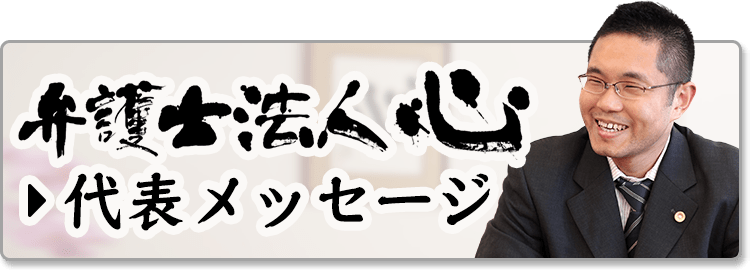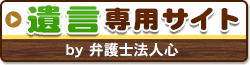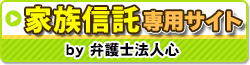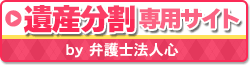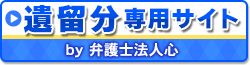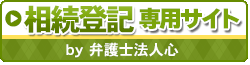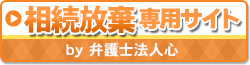遺留分の放棄に関するQ&A
遺留分の放棄とはなんですか?
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を放棄することを言います。
遺留分とは、簡単に言うと、相続人に最低限保証された権利のことを言います。
たとえば、遺言者で、相続人の1人には一切の財産を渡さないと記載したとしても、その相続人は遺留分の限度で、権利を有することになります。
他方、遺留分の放棄をしてしまうと、その相続人は、この最低保証の権利さえも受け取れないことになります。
遺留分の放棄はどのようにしますか?
遺留分の放棄は、被相続人がご生前中か、亡くなった後かによって、方法が異なります。
1 ご生前中の遺留分の放棄
ア ご生前中の遺留分放棄には裁判所の許可が必要
被相続人がご生前中の場合は、家庭裁判所での許可が必要となります。
そのため、家庭裁判所の許可がない限り、たとえ、生前に相続人が「遺留分請求はしない」と約束していたとしても、遺留分を放棄することにはなりません。
イ 遺留分放棄が認められる基準
次に、遺留分放棄が認められる基準なのですが、一般的には、以下の3つの点、全てを満たしている必要があります。
① 遺留分権利者が自らの意思で遺留分を放棄すること
② 遺留分放棄の理由が客観的に合理的であること
③ 放棄する遺留分と同等程度の代償があること
それぞれの要件について、①については、遺留分を有する相続人(遺留分権利者といいます)が、他の相続人等の脅迫、詐欺等によらず、自らの意思で遺留分放棄をすることが必要という意味です。
②については、③に関連することですが、遺留分を放棄することに合理性がある必要があります。
例えば、生前、被相続人から財産を多くもらっていたため、遺留分については、事前に放棄するといった理由が必要です。
最後に、③については、遺留分権利者が、被相続人から遺留分額と同程度の財産を受け取っている必要があります。
このように、ご生前中の遺留分放棄は、裁判所での厳格な審査が必要になるため、簡単に遺留分放棄が許可されるとも限りません。
ウ 遺留分放棄の手続き
遺留分放棄をする際は、裁判所に戸籍等の必要書類一式を提出します。
詳しい書類等は、裁判所のホームページに載っておりますので、ご確認ください。
書類一式を提出し、家庭裁判所に受理されると、審問(しんもん)の日程の連絡が来ます。
審問とは、簡単にいうと、裁判官との遺留分の放棄についての面談のようなものです。
その後、審問の結果、遺留分放棄が相当と認められれば、遺留分放棄の許可がでます。
許可がでると、許可しましたという裁判所からの通知が送られます。
2 亡くなった後の遺留分の放棄
相続が開始した後は、ご生前中の遺留分放棄とは異なり、家庭裁判所の許可は不要です。
そのため、遺留分の放棄の意思表示をすれば、遺留分を放棄することが可能です。
具体的な方法としては、遺留分を放棄するとの合意書を相続人間で作成する方法や、念書を作成するなど、書面で残しておいた方が良いでしょう。
遺留分放棄の撤回は可能ですか?
遺留分放棄をした場合、撤回することは可能です。
もっとも、被相続人が生前中の遺留分放棄の撤回については、遺留分を放棄した状態を維持することが客観的にみて不合理となった場合に、裁判官が職権で取り消しを認めることがあります。
そのため、この取り消しを認める場合についても、厳格な審査が行われますので、簡単に遺留分放棄が取り消されるわけではありません。
なお、亡くなった後の遺留分の放棄の撤回については、当事者が合意すれば、撤回が認められます。
相続放棄手続きにかかる費用に関するQ&A 遺留分の時効についてのQ&A